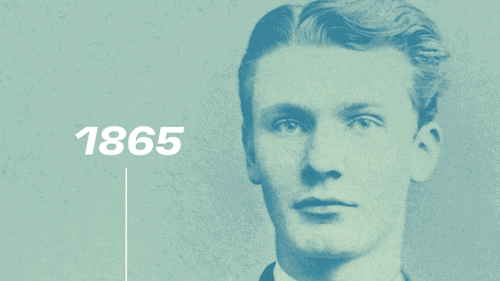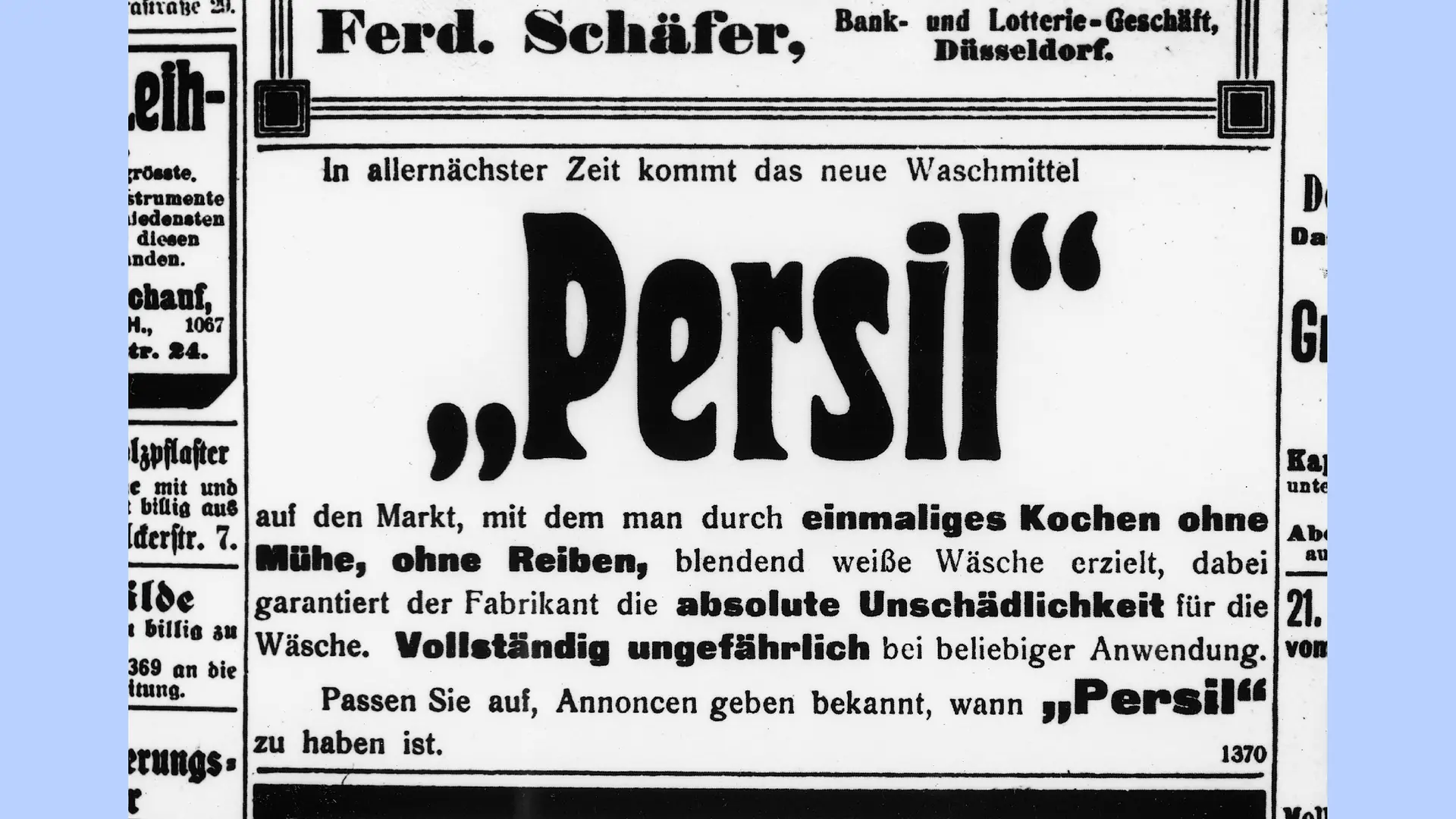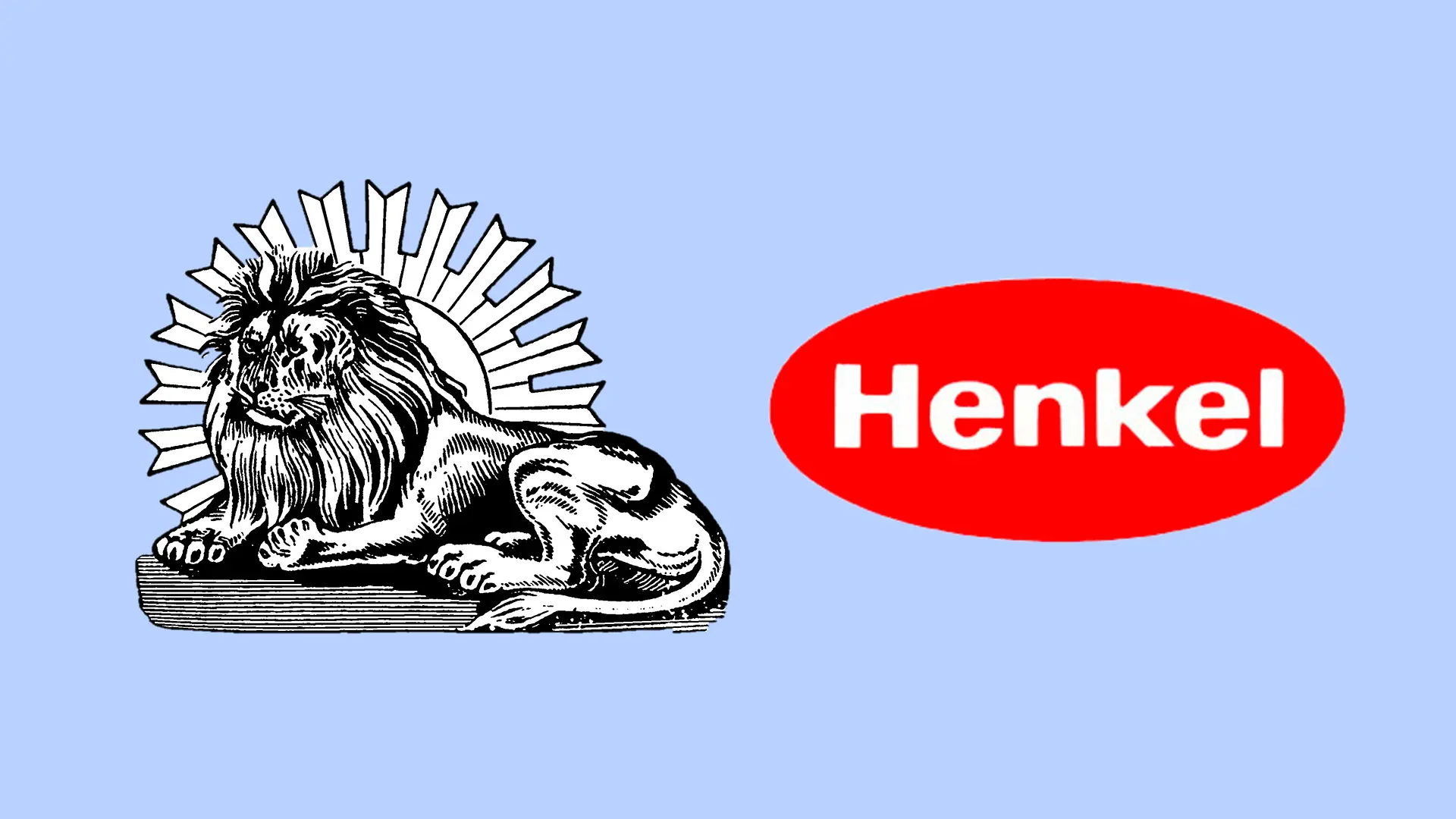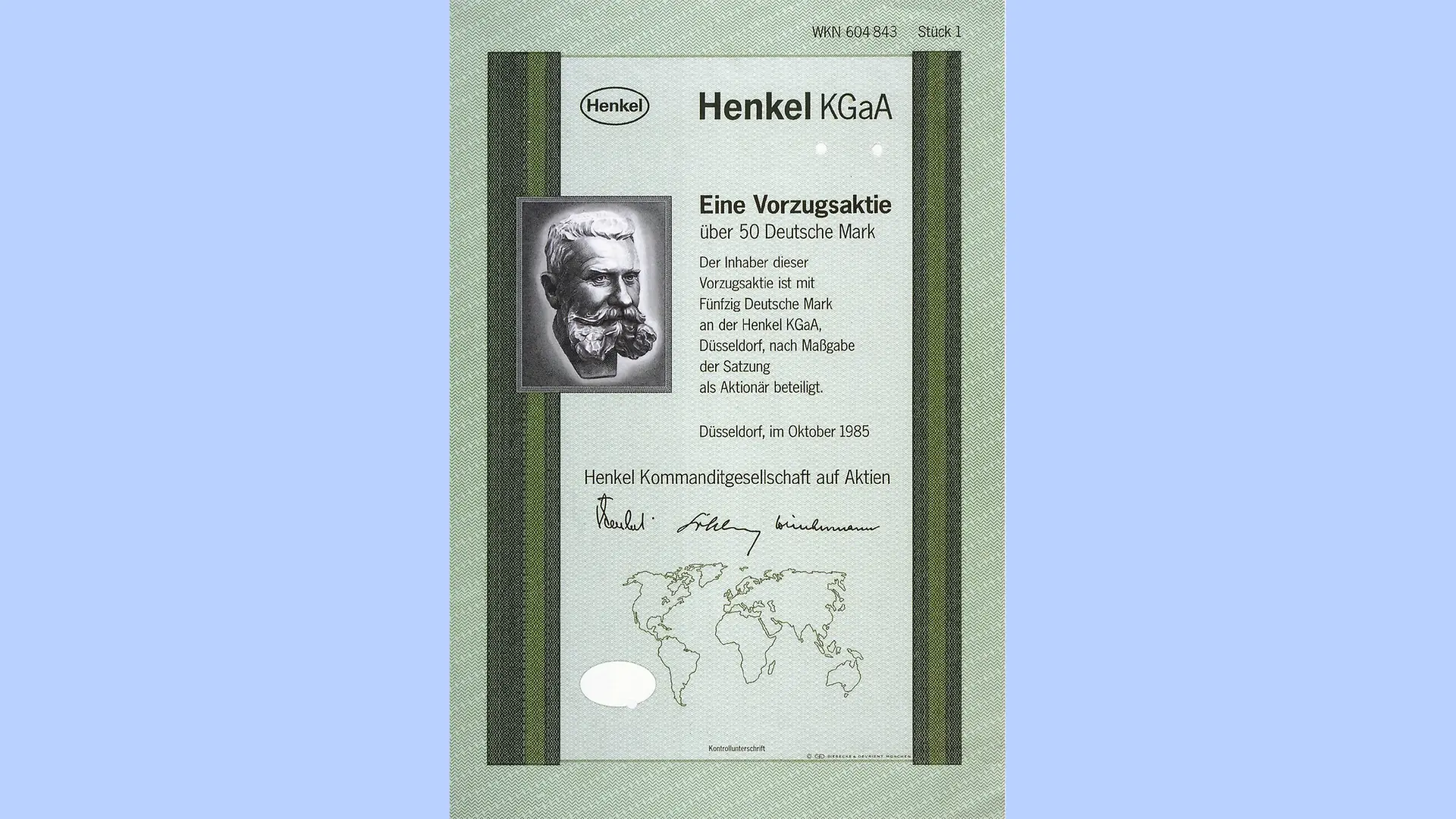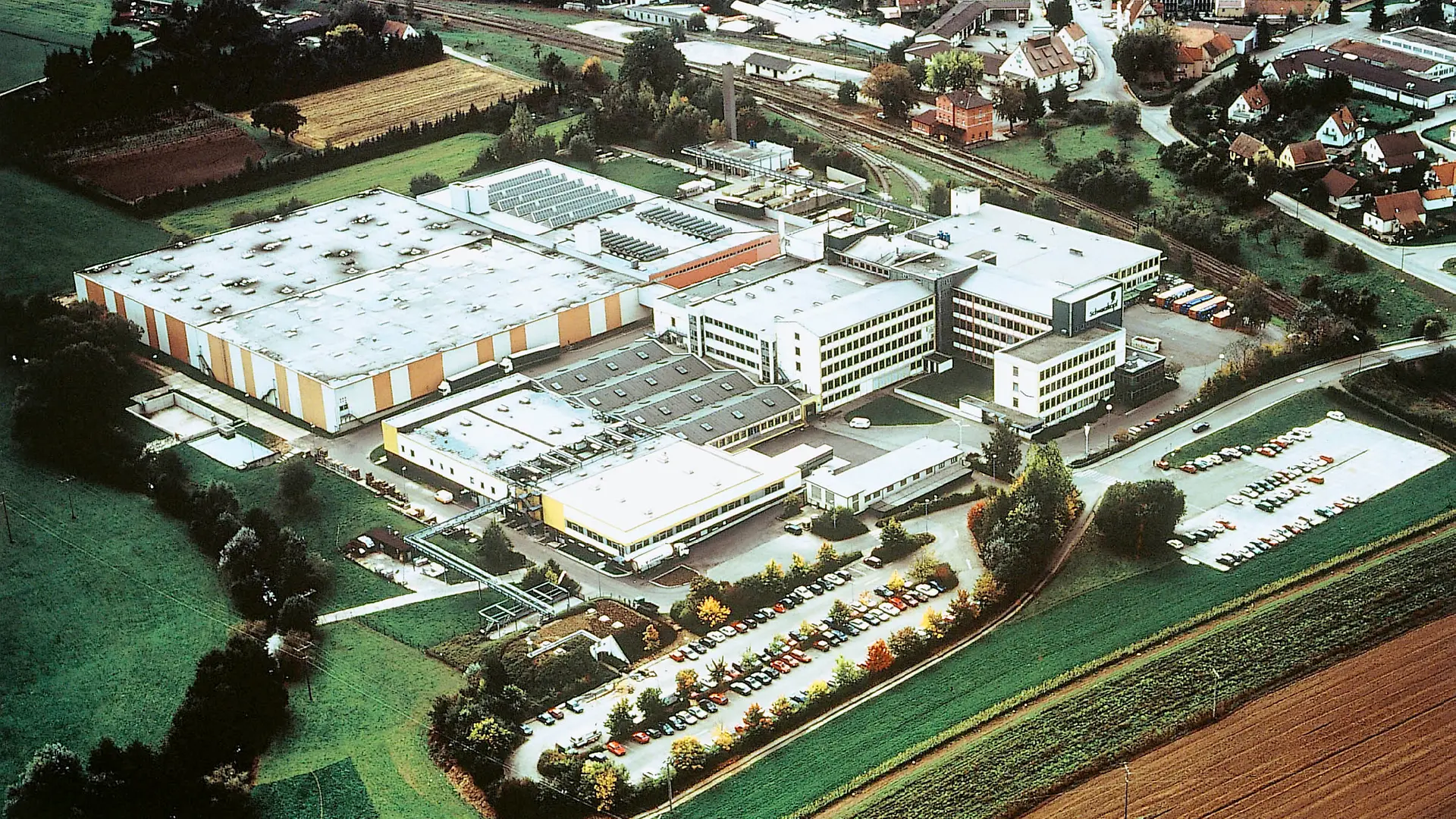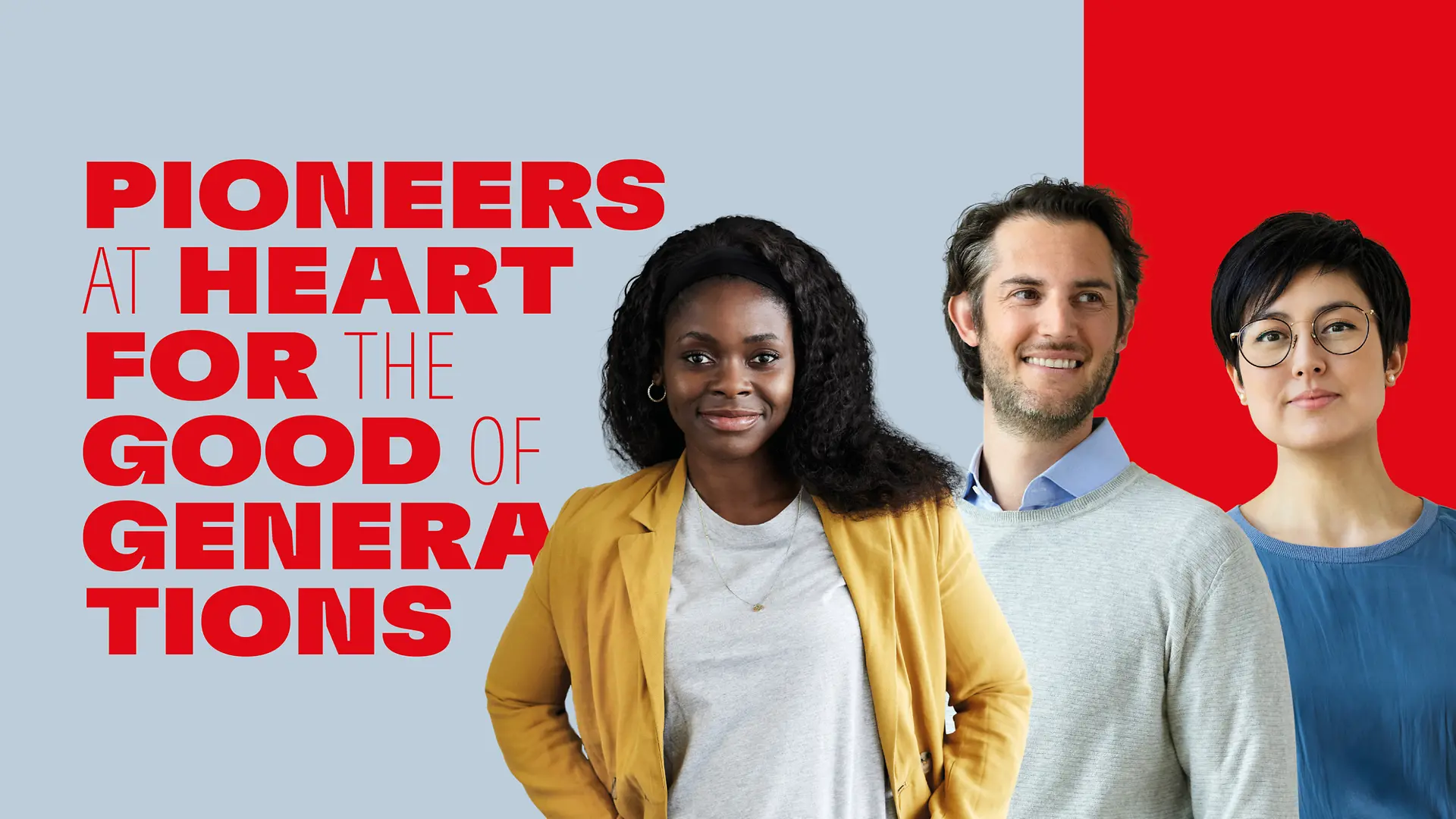ヘンケルと国家社会主義
国家社会主義に対する姿勢は会社も主要な創業家メンバーも同じで、当初は低姿勢で実利的に適応しながら協力していました。
元々はリベラル派としてドイツ社会民主党(DDP)で政治活動を行っていたヒューゴー・ヘンケルが、1930年にヘンケルの経営を引き継ぎました。ヒューゴーは起業家として、技術、効率性、グローバル市場の開拓を特に重視していました。1933年に政権を掌握した国家社会主義ドイツ労働党(ナチス)をヒューゴーは懐疑的に見ていましたが、同年ナチスに入党。後の発言で会社を守るためだったと話しています。当時目撃していた人たちの話からも、ヒューゴーが政治的干渉を回避しようとしていたことが裏付けられています。
それにもかかわらず、ヒューゴー・ヘンケルはすぐに政権に順応し、1942年までナチス関連の委員会で活動を続け、ヒトラーを公然と称賛しました。会社としても、プロパガンダ運動に参加しました。1938年、ヒューゴー・ヘンケルは税問題を背景に、甥のウェルナー・リュプス(1906年~1942年)によって会社の経営から追放されました。
ただ、この時期は総じて、会社経営陣、創業家メンバーからの政治的発言は例外的なものにとどまっていました。創業家内には明確な政治思想はありませんでしたが、それよりも、当時実業界に広がっていた実利的な機会主義の考えが強くなっていました。
ヘンケル社員の政治的姿勢
ナチス時代においてはヘンケル社員の政治観も一様ではなく、当時の社会的緊張と混乱を反映していました。
1933年に行われたワークスカウンシル(従業員代表組織)の選挙では、労働者階級の社員の大半(66.5%)が社会民主党に投票した一方で、ホワイトカラーの社員はナチスを支持する傾向が強く、ホワイトカラーのグループではナチス党員が5席のうち4席を獲得しました。当時のカウンシルの議長ヴィクトル・キルベルグによると、ホワイトカラーの社員のナチス支持者の割合はその後90%近くまで上昇したといいます。
特に取締役、技術者、部門長といった幹部の多くがナチスに入党していました。党員であることが、キャリアアップには不可欠となっていったのです。
ワークスカウンシルは、代表選挙では社会民主党が圧倒的な支持を得たにもかかわらず、1933年5月には政権への同調を余儀なくされました。キルベルクは議長の座を失いましたが、その後も現場監督として雇用され続けました。新しく従業員代表組織として導入された「Council of Trust(信任協議会)」では、代表員はもはや自由選挙で選ばれるのではなく、経営陣とナチス企業細胞組織(NSBO)によって決められました。1934年と1935年に行われた名ばかりの選挙は支持が得られず、1936年に破棄されました。
社員の政治的姿勢は依然として曖昧なものでした。多くの社員は、求めに応じてナチスのイベントに参加していましたが、特に管理職層などには確固たる支持者もいました。
ウェルナー・リュプス時代のヘンケル
1938年、ウェルナー・リュプスは会社内で中心的存在となりました。創業者の孫であるリュプスは早くからナチスに入党し、党員との緊密な関係を築き、その関係を戦略的に利用して会社内での地位を確立していきました。
リュプスは地位を固めたことで、1936年以降、税問題をきっかけに求心力が落ちていた叔父のヒューゴー・ヘンケルの失脚を図ります。リュプスは、ヒューゴーを不利な立場に陥れるための材料を集め、ナチス党員の協力の下、1938年夏、ヒューゴー・ヘンケルを経営トップからの辞任に追い込みました。ヒューゴーは監査役会へと移らざるを得なくなり、会社の方針に対する影響力は失われました。
リュプスが経営を引き継ぎ、ナチス政権寄りの経営方針へと導きました。1940年に、ヘンケルは「国家社会主義モデル企業」に認定されます。リュプスは自身を模範的な経済指導者として売り込み、会社で大規模なプロパガンダイベントを開催しました。起業家としても野心的な目標を掲げ追及しており、ヘンケルをIGファルベン社に次ぐ第二の化学企業へと成長させるため、デグサ社の買収も目論んでいました。しかし、彼の強引な戦略と経営スタイルは、社内だけでなく、ヘンケル創業家の双方から大きな反発を受けました。
1942年に社内の抗争がエスカレートしたため、リュプスは、再びヒューゴー・ヘンケルを非難しようと図りましたが、株主の過半数の意向により、経営トップの職を解任されました。そしてその直後、自動車事故で亡くなりました。リュプスが亡くなった後、ヒューゴー・ヘンケルの長男ルヨスト・ヘンケル博士(1909年~1961年)が「工場長」に就任、ヘルマン・リヒター博士(1903年~1982年)が執行役会議長を引き継ぎました。1945年以降、会社はリュプスとの関係性に一線を引き、彼を「黒羊」(厄介者)として描いています。しかしこれは、より広い責任の所在を無視した単純化されて見解でした。
国家社会主義時代のヘンケルにおける「アーリア化」
ナチス時代、ヘンケルは経済的利益を得るため、ユダヤ人が所有する企業を収用する「アーリア化」に数回関与しました。目的は、原材料へのアクセスの獲得、生産能力の拡大、市場シェアを確保することでした。通常は、Dreiring(ドライリング)やDehydag(デハイダック)などの子会社を通じて間接的に関与しましたが、フランクフルト(オーデル川沿い)、ウィーン、プラハ、ダンツィヒなどの企業が影響を受ける場合もありました。
1945年以降、ヘンケルは、「アーリア化」における役割を相対化しようと試みましたが、一部のケースでは賠償金を支払わざるを得ませんでした。コンラート・ヘンケルの学校での友人の母親を助けるなど、ユダヤ人市民を援助したケースもありましたが、会社が「アーリア化」に参加したという事実は変わることはありません。
国家社会主義時代のヘンケルにおける強制労働
第二次世界大戦中、大多数のドイツ企業と同様、ドイツ国防軍(Wehrmacht)の徴兵による労働不足を補うために外国人の強制労働を行いしました。これには、フランス、ベルギー、イタリア、ポーランド、ソ連などの国々から労働事務所や軍事機関、強制徴用などを通じてドイツに連れてこられた民間人や捕虜も含まれていました。
デュッセルドルフ市ホルトハウゼン地区の工場において、強制労働者の割合が最も高かったのは1943年12月31日の15.8%でした。他の場所では50%を超えることもありました。民間人の強制労働者は企業所有宿舎に収容される一方、捕虜の強制労働者はドイツ国防軍が管理する施設に収容されていました。
生活環境、労働環境は、かなり異なっていました。西側連合国の捕虜の場合は概ね国際条約が順守されていましたが、ソ連人の捕虜やいわゆる「東欧諸国からの労働者」の場合は劣悪な環境下での労働が強いられました。そうした強制労働者は、通常、国別のバラック収容所に収容されていました。労働時間は週に47時間から60時間までの幅がありました。
ヘンケルは、ほぼすべての部門において強制労働者を使役し、厳重な管理下に置いていました。ドイツ人との接触は禁止されており、違反すると厳罰に処されました。デュッセルドルフ市ホルトハウゼン地区のヘンケルでは3人のソ連人の捕虜が亡くなっています。内2人は化学物質の誤飲による中毒死とされており、もう1人は脱走を試みたところをドイツ国防軍の見張りの兵に撃たれて亡くなっています。戦後、当初は「東欧諸国からの労働者」を中心に多くが収容所に留まり、難民とみなされました。
ヘンケルはドイツの他の企業とともに、2000年に「記憶・責任・未来」基金に加盟しました。1990年代末、ヘンケルにおける過去の捕虜・強制労働者の使役について包括的な外部調査が実施され、2001年にヘンケルの社史「Menschen und Marken」(人とブランド)に掲載されました。
まとめ
ナチス政権下の国家社会主義時代におけるヘンケルの歴史は、本来はリベラル派だった家族経営企業が、次第に独裁政権に順応していったケースの一例です。他の多くの企業と同様、ヘンケルの責任を担っていた者たちが経済的視点だけで行動し、道義的責任のほとんどを無視していたのです。当時の社員については一様ではなく、多くは単に従っていただけですが、社員や管理職の間ではナチスへの支持が高かったのです。ヘンケルにおける政治的スタンスの変化は、当初は一定の距離を保っていたはずが、実利を重んじて順応し、ナチス政権に関与するようになるという、当時のドイツ大企業の多くがたどった道といえます。